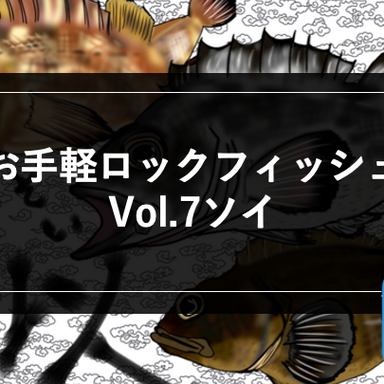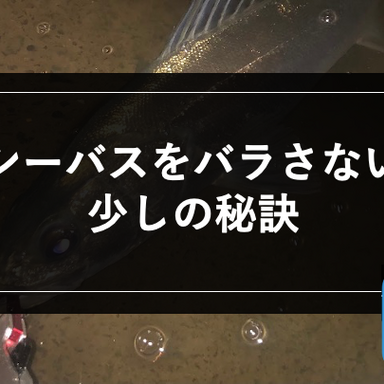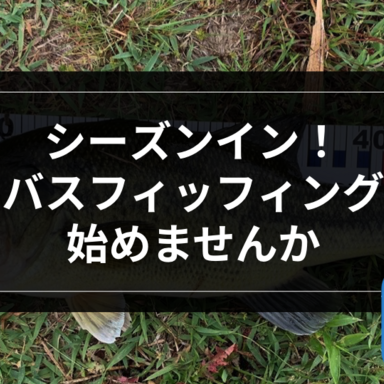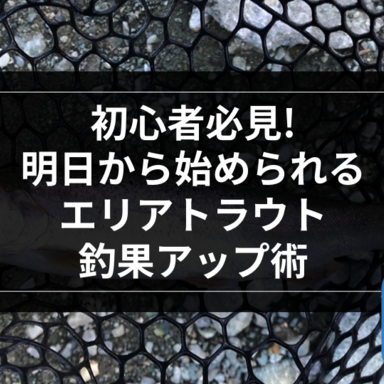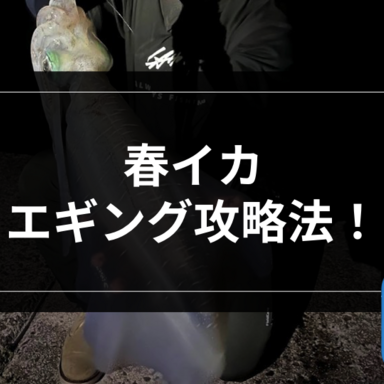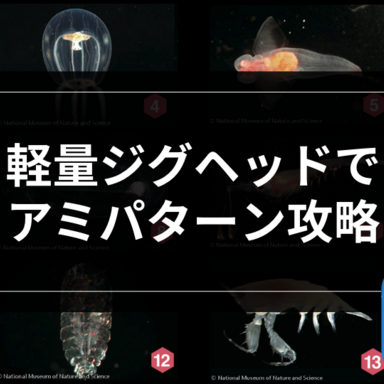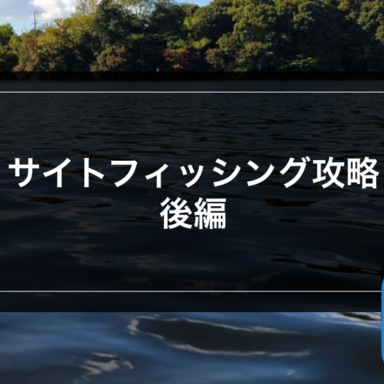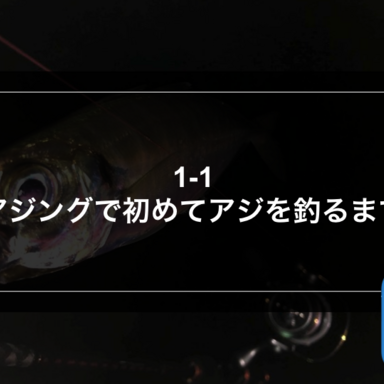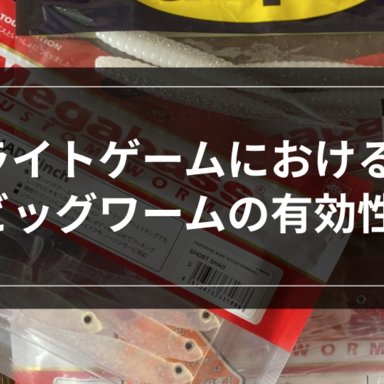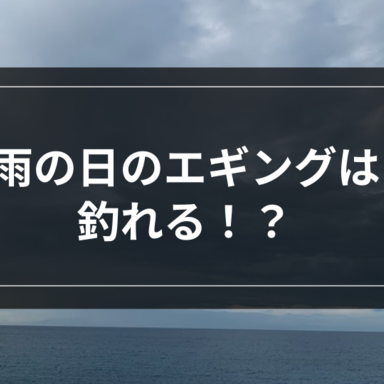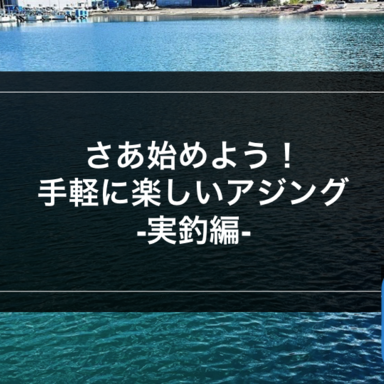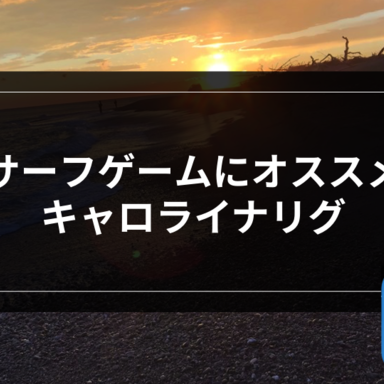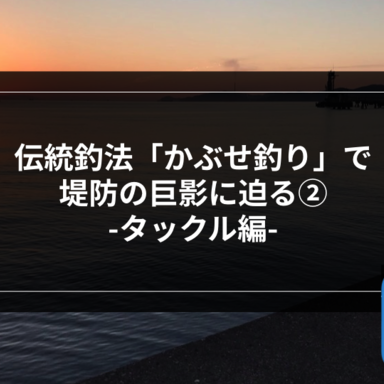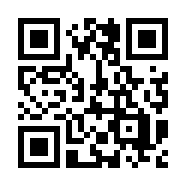さて、渓流シーズンも後少しで終わりの9月後半。
しかし、渓流が終われば他の釣りがやってきます。
今回紹介する釣りは、すでにもう始まっているアオリイカ!!
年中を通して一番釣りやすいこの時期だからこそ、ショアエギング、ボートエギング、ティップランを今年から初めてみませんか?
ちなみにトップ画像のアオリイカは、seao_orionさんの2020/09/27の釣果です。
キレイでしたので採用させていただきました。
アオリイカは年魚と同じ

アオリイカの寿命って1年だと知っていましたか。
春に卵を産んで、夏前には死にます。
卵から生まれたイカは、早くてお盆過ぎから、遅くても9月前半までには釣りものとして成立する大きさまで成長します。
エギングやっている人からすると常識的な話にはなると思いますが、念の為に以下にwikipediaを貼り付けておきます。
胴が丸みを帯び、胴の縁に渡って半円形のひれを持つ。
外見はコウイカに似るが、甲は薄くて透明な軟甲である。雄の背中には白色の短い横線模様が散在するが、雌は横線模様が不明瞭である。
標準和名のアオリイカは漢字では障泥烏賊と書くが、この名前は大型で幅広であるひれの形と色が障泥(あおり)と呼ばれる馬用の革製鞍側面下側部位、もしくは鞍の下で胴体に巻く泥よけの馬具に似ており、またイカの脚部がちょうどその取付紐に似ることによる。
wikipediaを否定するわけではありませんが、【外見はコウイカに似るが】とありますが、全く似てないと思いませんか。
コウイカなどはゲソ部分が圧倒的に短いので、ひと目見てわかるような。
もちろん、同じイカと言う意味では似ていますがね。
また、僕の見解では多くのアオリイカは1年で死ぬと言われていますが、2年間以上生きる個体もいると思っています。(希望的推測)
以前に秋口に小さな個体に混じって、明らかに大きな個体を見たことがあるからです。
年魚と言われる魚の多くは生殖行動で体力を全部使い切り息絶えるものが多いですが、他の魚でも生き残る個体がいることは明らかになっています。
それと同じで、生殖行動をしなかった個体は2年目に突入するのではないか、また生殖行動をしても2年目にいくやつがいるのではないかと思います。
もしも、このマガジンを読んで釣りにいき明らかにおかしな個体が釣れた場合は報告をお待ちしております。
アングラーズでは、こういった釣り人しか持ち得ない情報が集まる素敵な場だと思っていますので。
今後は、狙っている生物の生態調査までできたらいいですね。
ベストシーズンは春と秋
アオリイカのベストシーズンは春と秋ですが、これには生殖行動=産卵という理由があります。
秋に生まれて春に産卵するというサイクルを繰り返すアオリイカは、このビッグイベントのために多くの個体が接岸します。
春に接岸する理由は、生まれてくる子供のために比較的浅場で産卵するため。
秋に接岸している理由は、大きくなるまで浅場で餌を獲るため。
どちらの時期も、他の時期に比べ浅場にいる可能性が高いため、ショアから釣りやすくなります。
また、春は数は釣れにくいですが比較的大きな個体を。
秋はサイズは期待できませんが、その代わりたくさんのアオリイカを釣ることができます。
その結果、春と秋それぞれにメリットがありますが、初めての1匹を釣るのにベストなのは秋と言えると思います。
他の釣りに比べて、【エギを抱く】という感覚が難しいと思います。
その感覚に慣れるまでは、秋の時期になるべく多くのアオリイカを釣ることがオススメ!
今、アングラーズでアオリイカを検索すると大量の釣果が出てきます。
この釣果を見れば釣れていることがわかると思います。

アオリイカの締め方
締め方にはたくさんの方法があります。
ただ、すべてに言えることは、持って帰る場合は必ず〆(しめ)ましょう。
アオリイカにとっても僕らにとっても、それが最良の方法です。
ただ、この締め方については道具を使ったり、使わなかったりとたくさんの方法が色んなメディアで紹介されていますが、ぶっちゃけ
『道具なんて使わなくても手で〆ることができますから、買わなくていいです。』
ちなみにエギを使って〆る方もいると思いますが、手で触りたくない(汚れるとか)方はエギでもいいです。
僕は普段は手でやります。
覚えてしまえば簡単なことなので、是非覚えましょう。
大変、わかりやすい動画がありましたので、こちらを紹介します。
コツは上半分と下半分で〆る場所が違い、【上半分はつまむ、下半分は押す】です。
アオリイカの別名、地方名
アオリイカには別名、地方名がたくさんあります。
場所によっては出世魚のようにサイズで言い方を変えている場所もあります。
とりあえず、わかる範囲での呼称の違いを書いてみます。
- モイカ(愛知、高知)
- シルイチャー(沖縄)
- ミズイカ(長崎)
- バショウイカ(西伊豆)
- 他にも、クツイカ、シロイカ、ホヤイカなどあるらしい
ちなみにアオリイカにはアカイカ型、シロイカ型、クワイカ型の3種類があるらしいです。
この辺りは全く詳しくないので、説明できないのですが僕はメバルが3種類あるように、遺伝子的に3種類のアオリイカが日本にはいるんだな程度しか考えていません。
むしろそんなことよりも厄介なのが、呼び名の方です。
例えば、アオリイカをシロイカと呼んでいる地域もあるが、そもそもシロイカと呼んでいるケンサキイカもいます。
イカは地方名が多すぎるだけではなく、同じような呼び方をしている場所が多すぎることでカオスな状況が生まれています。
もっと呼び名をまとめてほしいな。

イカを釣ってたべよう
釣り方を説明しないマガジンがあってもいい。と勝手に肯定しておいて。。。
まだ、アオリイカを釣ったことない人がいれば是非釣りに行ってみてはいかがでしょうか。
また是非食べてほしいです。
アオリイカがイカの王様と言われる所以がわかると思います。
適切なサイズを、適切な方法で〆て、しっかりとクーラーに入れて持ち帰りましょう。
普段は魚を捌いたことがない人でも、とてつもなく簡単にアオリイカを捌くことができますよ。
この秋は、是非アオリイカにチャレンジしてみてください。
また次回以降に釣り方についてもまとめたいと思います。